|
高校を卒業してからも、彼と背格好が似ている人や声が似ている人がいると立ち止まった。希望混じりに目を凝らし、耳を澄ましてみても私が一番会いたい人には会えなかった。 彼を目で捉えた時、6年もの間なぜ恋愛ができなかったのか、わかったような気がした。どうしてあの時自分を避ける理由を聞いていなかったんだろう。
Before All Slow Down 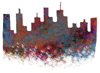
二次会の会場へ戻ると私の友達と門田くんは相変わらず話に華を咲かせていた。私と平和島くんが戻ってきた事に気付いた友達が手招きをする。 「これ、二人の分もらっといたから。ハイ。」 ありがとう、と言うと友達は笑って私と平和島くんにビンゴゲームの紙を渡した。二次会では定番のビンゴが始まるらしい。真ん中のマスを開けると、視線を感じたのでその方向を見ると見覚えのあるスラリとした眼鏡姿の男の人が立っていた。 「あれ…?岸谷くん?」 「覚えててくれたんだね。」 にこっと笑顔で話し掛けてきた岸谷くんと会うのも卒業以来で6年ぶりだった。司会者がビンゴの数字を読み上げていくのが聞こえ、少しずつマスが開けられていく。岸谷くんは隣のクラスだったけれど、保健委員が一緒だったので少し話した事がある。聞くと、新郎がケガをする度に手当てをしてあげていたらしく、門田くんに岸谷くんへメールを回すように頼んだそうだ。そういえば、新郎は人気者で敵を作らない様なタイプなのによくケガをしていた気がする。 「彼ね、正義感が強いからよく静雄の喧嘩を止めにいってたんだよ。結局自分だけケガしちゃってたんだけどね。」 「そうだったの?」 隣にいた平和島くんをちらと見ると少しばつの悪そうに横を向いていて頭を掻いている。 「別に静雄が悪いわけじゃないからね。喧嘩だって買わざるを得ない状況しかなかったし、首つっこんでたのは新郎くんの方だからさ。ケガしない様に庇うの大変だったみたいだしね。」 「…止めに来る割に弱かったからな。」 「でも、そんな人だからちゃんとお祝いしに来たんだろう?」 岸谷くんがそう言うと平和島くんは腕を組んで静かに息を吐いた。高校時代には知らなかった事実で、私はなぜか少し嬉しくなっていた。こうして平和島くんの事を理解している人が周りに沢山いるのだと。岸谷くんは私の方へ向き直って言葉を続ける。 「さん、雰囲気が変わってたから気付かなかったよ。綺麗になったね。」 「そんな事ないよ、全然変わってないし。」 「ま、元々美人さんだったから気に障ったなら謝るけど…て、ちょっと待って、静雄…何か怒ってる?」 と、岸谷くんが平和島くんに話し掛けた所で、読み上げられた数字を照らし合わせると自分の紙がビンゴになっていた。 「あ、私ビンゴです。」 「なんだよ、その気の抜けた報告は。」 逆隣にいた門田くんが少し笑ったのを見届けながら司会者の方へ行くと有名店のバームクーヘンを渡された。既に特賞や上位は出てしまっていたが、賞品が当たるのは嬉しい。 「いいなーここの店のって行列できてて中々食べられないんだよー。」 「そうなの?」 「えっ知らないの!?だったら私がもらうー!」 「やだやだ、私食べたい!」 当たった人を蚊帳の外にして、友達同士でバームクーヘンを取り合い始めたので笑ってしまった。すると平和島くんと一瞬目が合ってどきりと心臓が跳ねた。その表情は初めて見るもので、優しく笑っていたような気がした。そしてまた数字が読み上げられる。 「お。」 「あ、ビンゴ?」 そうだな、と言って平和島くんも同じように賞品を読み上げる司会者の元へ歩いていく。そして帰ってきた平和島くんは少し困った様な顔をしていた。 「当たったのに浮かない顔してるけど…嬉しくないの?タジン鍋。」 「あんま自炊しねぇんだよ。置く場所もあんまりねぇし…。」 確かにタジン鍋は蓋も大きくて収納に困るかもしれない。しかし同級生の幹事が用意してくれたもので、無下にもできないのだろう。そして、私はふと思いついた。 「平和島くん、私のと交換しない?」 「……。」 「バームクーヘンなら食べたらなくなるものだし、置き場所困らないよね。」 「あぁ…そうだな。」 「あと、結構甘い物好きじゃなかった?」 「……なんで、んな事覚えてんだ?」 「なんでだったかな…とりあえず平和島くんは甘党だったっていう事だけ覚えてるんだけど。」 平和島くんは少し驚いていたけれど、私もよく思い出せない。思い出せないものは仕方がないと思い、椅子に置いていたバームクーヘンの袋を平和島くんに渡した。すると友達がって、そんなに平和島くんと仲良かったっけ?と呟いたのが聞こえた。更には3年の途中までは普通だったけど…という別の友達の声まで耳に入って、自分以外の人の目にもそんな風に映っていたのか、と思った。 そして門田くんを見ると先ほどとは違った含みのある笑みを見せた。この目はまさか、全部知っているのではないだろうか。そして平和島くんはタジン鍋の入った袋を私に渡した。タジン鍋は元々欲しかったわけではないが、母親が欲しいと言っていた事を思い出したのだ。 「ありがとう、私、鍋欲しかったんだ。」 「…それ本当か?」 「うん?そうだよ。作るのお母さんだけど。」 その言葉を聞いた平和島くんはふっと優しく笑った。ドキドキするのに、どうしてこんなに平和島くんの笑顔を見れるだけで嬉しくなってしまうのだろう。高校の時に話せなかった分、反動がきているのかもしれない。 「うー…重い…。」 二次会がお開きになると、女性陣は引き出物の重さに四苦八苦していた。一気に人が外に出て行くので、少し見送ってから私たちは外に出ることにした。門田くんが食器とか入ってるんじゃねぇか?と声を掛けて友達の分を持とうとしている。波が少し落ち着いた所でさて、と自分の引き出物とタジン鍋を持っていこうとした時には、椅子にあったはずの荷物がなかった。そして、既に平和島くんが腕を肩に掛けて軽々と持って歩いているのが目に入った。引き出物の袋は皆一緒だけれど、それと一緒に持っているのはさっき平和島くんに渡されたタジン鍋が入っている袋だ。それに気付くと慌てて駆け寄った。 「ごめん!平和島くん。」 「…ん?」 「あの、荷物…ありがとう。」 「あぁ。」 そもそも俺が当てた鍋なんだし。と言って平和島くんはドアを開けてから抑えると、先に外に出る様に促した。大袈裟かもしれないが、これではまるでお姫様みたいだ。こんなに色々とスマートにこなせるようになっているなんて、とまた心臓の心拍数が上がっている事に気付いた。 外に出てから式から出ずっぱりの女性陣は疲労の表情を見せていた。 「まぁ、皆同じ方向だろ?持ってやるから。」 「さぁっすが門田、優しい~。」 「そうやって何人の女の子を虜にしてきたんだか…。」 「虜になんざしてねぇよ。」 「はい、岸谷くんも一つ持ってね。」 「ちょっとは遠慮っていう言葉を知ったらどうかな?」 引き出物を持たされた岸谷くんは溜息を吐きながらも、しっかりと持ってあげている。苦笑いをした門田くんは私の方を一瞬見ると、平和島くんに話し掛けた。 「お前はを送ってくだろ?一番重そうだしな。」 「……あぁ、そうだな。」 「あ、でも私の家、逆方向なんだよ。卒業してから引っ越してて…。」 「いいから、送ってく。」 平和島くんはそう言うと門田くんたちとは逆の方向へ歩き出した。やはり門田くんは全て知っている。私は高校時代からの級友に手を振って平和島くんの隣についた。
Are you ready...?
先ほどまでは周りに友達が沢山いた為、いつも通りに接する事ができていた。しかし、友達だと思っていた人から、しかも高校時代に好きだった人から告白されて平気でいられる人なんているのだろうか。ましてや私は彼氏もいなければ、好きな人もずっといない。普通に会話がしたいと思うのに、二人きりだとどうしても意識してしまってどんな会話をすればいいのかわからない。高校時代、私は平和島くんとどんな会話をしていたのだろう。きっと口数の少ない彼に私が話し掛けていたはずだけれど、考えれば考えるほど頭は冷静に働いてくれない。 「…なぁ。」 「えっ?」 頭を必死に働かせていると隣を歩いていた平和島くんが口を開いた。 「困らせようと思って言ったわけじゃ、ねぇんだよ。」 「…えっあ、うん。」 「返事、急がなくていいから。」 「……はい…。」 気の利いた言葉が全く出てこず、私は自己嫌悪に陥った。私より、平和島くんの方がよっぽど大人だ。こんな風にパニックに近い状態で一挙一動を意識してしまうなんて、まるで中学生みたいだ。 私の家の前に着くと、平和島くんは携帯電話を取り出した。 「番号、いいか?」 「あ、そうだよね。」 バッグから携帯電話を取り出して番号を交換した。「平和島静雄」と新しく電話帳に追加された名前を見ただけで緊張してしまうのはなぜなのだろう。すると、声に気付いたのか玄関のドアが開く音がして、母親が出てきていた。 「?結構早かったのね?……あら、あらあら?」 私の姿を確認した直後に隣にいる平和島くんを視界に捉えると、母親は興味深々といった様子でこちらに近づいてきた。表情から察するに絶対に何か勘違いをしている。 「荷物が多いから送ってもらったの。」 「まぁまぁ、いい人がいるんなら言いなさいよ!いつもがお世話になってます。」 「や、今日6年ぶりに会ったからそういうんじゃないんだけど…。」 「平和島静雄です。」 そう言うと平和島くんはきちんとお辞儀をした。それを見て6年の歳月はすごいなとつくづく感じた。こんな風に目上の人に接する平和島くんを見るのも初めてだった。 「いつでも遊びに来てね、平和島くん。」 母親はにっこりと笑って言った。社交辞令の常套句だが、おそらく本気で言っている。ずっと彼氏のいない私に対して、一体いつになったら孫の顔が見れるのかと耳がタコになる程聞かされてきた位なのだ。そこでありがとうございますとでも言うのが、これまた社交辞令なのだろう。だが、放たれた言葉にまた私は言葉を失う。 「また来ると思うので、これからよろしくお願いします。」 母親はまぁ、と驚きと嬉しさを滲ませて声を上げた。これっきりではないという事をハッキリと言われたようなもので、どんどん顔に血が登って熱くなっていくので俯く他なかった。平和島くんの方をまともに見る事すらできない。 じゃ、俺はこれで。と再び頭を下げてから後ろを向いた平和島くんに慌てて声を掛けた。 「送ってくれてありがとう!」 そう言うと少しこちらを向いてまたな、と笑って歩いていった。 話し足りなかった。本当はもっと話したかった。まだ一緒にいたかった。背中が遠くなるのが寂しかった。そんな感情を持つ自分に気づいた。そう思う間にもどんどん平和島くんの姿は小さくなっていく。 きっと私は今日も、明日も、明後日も平和島くんの事ばかり考えているのだろう。そして、返事を保留にする理由がどこにもなくなっている事に気付いた。 「…すぐ、戻ってくるから。」 母親に一言だけ残し、気付くと私は遠くなってしまった平和島くんの背中を追って走っていた。ヒールの音が夜道に響く。一秒でも早く伝えなければ。全てが遅くなってしまう前に。もう二度と後悔はすまいと心に決めて。
I can't stop anymore.
|